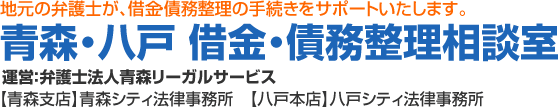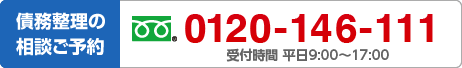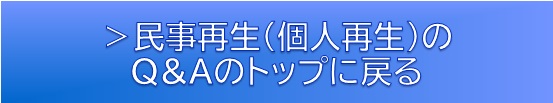それぞれの場合における住宅資金特別条項付個人再生の利用の可否は、以下のとおりとなります。
1 主債務者の住宅資金特別条項付個人再生について
それぞれの場合における住宅資金特別条項付個人再生の利用の可否は、以下のとおりとなります。
1 主債務者の住宅資金特別条項付個人再生について
主債務者については、要件を満たせば住宅資金特別条項付個人再生を利用することが可能です。
この点、住宅ローンの契約書では、主債務者が個人再生などを行えば、債権者は連帯保証人に対して残額を一括請求できる旨が定められているのが通常です。
しかし、住宅資金特別条項付個人再生を利用した場合、主債務者が住宅ローンの返済を継続する限り、連帯保証人に対する一括請求は行われません(民事再生法203条1項、177条2項)。
そのため、安心して住宅資金特別条項付個人再生を利用することができます。
2 連帯保証人の住宅資金特別条項付個人再生について
連帯保証人については、住宅資金特別条項付個人再生を利用することはできません。
連帯保証人が負っている連帯保証債務は住宅ローンの債務そのものではなく、住宅資金特別条項付個人再生の要件を満たさないためです。
そのため、連帯保証人が個人再生を行う場合には、住宅資金特別条項付個人再生ではなく、通常の個人再生を行うこととなります。
ただし、住宅ローンの契約書では、連帯保証人が個人再生などを行う場合、代わりの連帯保証人を立てることや、主債務者が一括請求を受けることが定められていることもあります。
そのため、連帯保証人が個人再生を行う場合には、住宅ローンの契約書の内容を確認のうえ、連帯保証人の変更について住宅ローンの債権者と協議するなど、慎重な対応が必要となるでしょう。
3 主債務者と連帯保証人がともに個人再生をする場合
主債務者が住宅資金特別条項付個人再生を申し立てるのと同時に、連帯保証人が通常の個人再生を申し立てることもできます。
この場合、まず、主債務者は、住宅資金特別条項付個人再生の効果により、住宅ローンを減額されずに(住宅ローン以外の債務は減額を受ける)分割返済を継続すれば、住宅を手元に残すことができます。
一方で、連帯保証人が負う連帯保証債務は、住宅ローンそのものではないため、通常の個人再生の効果により、減額を受けるものの減額後の金額について分割返済の義務が残ることとなります。
そのため、主債務者と連帯保証人の住宅ローンの分割返済については、調整を図る必要が出てきます。
この点、連帯保証人の再生計画において、「主債務者がその再生計画のとおり毎月の支払をしたときは、連帯保証人の当該月の保証債務は消滅する。主債務者が前記の支払を怠ったときは、再生債権者から請求を受けた後〇日以内に弁済すれば足りる」との条項を設けることが考えられます。
4 ペアローンの場合
住宅ローンがペアローンの場合には、以上とは異なる考慮が必要となります。
詳しくは、下記の関連Q&Aをご覧いただければと存じます。